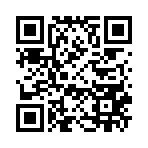2008年07月28日
アジとミョウガの酒盗あえ
 アジだけに、味のわかる酒飲みにお勧めな一品。
アジだけに、味のわかる酒飲みにお勧めな一品。だが……難点が一つある。それは材料に「酒盗」なるカツオの(内臓の)塩辛を使うため、少々材料がレアである。今回、たまたま相方が高知に出張に行ったので、手許にあった。甘口と辛口と二種類あったが、酒盗あえには迷わず「辛口」をチョイスした。こちらは塩とカツオだけで作られており、そのまま食べるとかなり塩辛い(ゆえに「酒盗」か?)が、あえるには余計なものが混じらない分最適である。
さてアジは普通にタタキの要領でさばいておく。ミョウガはアジ(中~大)一尾に対し、二本ほどを千切りにしてスタンバイしておく。
いよいよ酒盗の出番だ。大さじ2ほどの酒盗を包丁で存分に叩く。酒盗に入っている内臓はかなり歯ごたえがあるので、会える場合はよ~く叩くのが基本(らしい)。酒盗大さじ2を叩いたものに酒大さじ1を加え、レンジで一度温める。このあたりは参考にしたレシピ通りだが、好みで醤油なんかを少々加えてみるのも良いかもしれない。
一度温めた酒盗を十分に冷ましてから(冷蔵庫で冷やせばてっとり早い(^^ゞ)、準備しておいたアジ、ミョウガとあえる。最後にお好みでネギの小口をぱらりで出来上がりだ。もちろん醤油とかなしに、酒盗で旨くなったアジをそのまま楽しむのである。
あとは食べるだけ。確かにこの味、酒が進むなぁ~(笑) さすが「酒盗」の名を冠するだけのことはある。アジはカツオで旨くなる!
本来はカツオの身であえるらしいが、そこはオレ流アレンジってことで。アジでも相性バッチリですよ
 続きを読む
続きを読む2008年07月19日
超シンプル~なアジのタタキ
 アジといえば、何はさておき、まずはタタキでしょう。とにかく鮮度のいいうちにやりたいが、といっても沖釣り当日は、疲れてて凝ったことはしたくないという気持ちもあるし……(^^ゞ
アジといえば、何はさておき、まずはタタキでしょう。とにかく鮮度のいいうちにやりたいが、といっても沖釣り当日は、疲れてて凝ったことはしたくないという気持ちもあるし……(^^ゞそんなわけで、今日のタタキはなんの工夫もございません。
普通にアジを三枚におろし、小骨を全部骨抜きで抜き取り、皮を手で剥いだら、それをタタキのように切っていく。このときに釣って当日の身は結構固めなので、歯ごたえを考慮してやや薄めにそぎ切ってみた。
これが、まあ、言うなれば唯一の工夫(…というほどのこともないが)。
それを皿に盛り付けて、別に用意しておいた大葉と万能ねぎをみじん切りにしたものを上からばさっと天盛りにして、脇にすりおろしたショウガ(チューブ入りのものでも全く問題ナッシング)を添えて出来上がり。
薬味は最初から混ぜてしまっても良いが(というか、普通はそうするが)、とにかく疲れてて面倒くさかったので、食べる人が食べたいだけ混ぜてね、ってなスタイルにしてみた。つまり、手を抜いた(笑)
でも、どんだけ手を抜こうが、釣りたてアジのタタキは本当に旨い。ショウガや大葉の香りも相まって、さっぱりとした清涼感は、何物にも代え難い。だから、釣ったその日には是非この手抜きタタキがお勧め。
凝った料理は、十分休んでから翌日やるからさ……(^^ゞ チャンチャン
ちなみにこの時期のアジは決して脂乗りが良いわけではないが、アジのタタキとはさっぱりと食べるものだと思っているので、個人的にはむしろこれくらいが( ・∀・)イイ! 続きを読む
2007年10月26日
茄子のなめろう焼き
 しばらく溜めていた料理ネタもこれで一段落であるが、「スローライフとしての釣り」で紹介した雑誌「サライ」に「秋茄子のなめろう焼き」というオリジナルレシピが載っていた。今回の料理は、これを真似たもので、オリジナルのほうではアジではなくマイワシを使っていた。
しばらく溜めていた料理ネタもこれで一段落であるが、「スローライフとしての釣り」で紹介した雑誌「サライ」に「秋茄子のなめろう焼き」というオリジナルレシピが載っていた。今回の料理は、これを真似たもので、オリジナルのほうではアジではなくマイワシを使っていた。オリジナルレシピでは、茗荷やら、松の実やら、果ては山椒の佃煮まで入れていたが、我が一般庶民の家庭にそれらのものが常備されているはずもなく、なめろうは普通にアジに味噌、大葉、生姜を入れて粘りが出るまで叩いたものである。ただし普通のなめろうほど細かく叩かず、少し身の粒々感が残る程度がいいみたい!
さらにオリジナルレシピによると味噌は「ハナマルキ味噌」という指定があるが、これは単にスポンサーの関係と思われる
 まぁ引用させていただいた関係で、ここでも軽く宣伝させていただくことにしよう~
まぁ引用させていただいた関係で、ここでも軽く宣伝させていただくことにしよう~
さてなめろうを作ったら、なめろうの器ともなるナスの仕込である。写真では、ナスのへたをとってしまったが、オリジナルではつけたままだった。どうやらつけたままの方が、見栄えは良いように思われる。もし作る方がおられるなら、へたはつけたままにしておこう。文字通り「へた」なことをしてしまったものである・・・・・・

ナスは洗って、水気を十分に拭いたら、縦に深く一本、包丁で切れ目を入れる。それを170℃の油で素揚げにする。揚げることでナスの色がとても良くなるので、ここでの素揚げは、火を通すことより専らナスの彩りに気を使うべきである。
さて素揚げしたナスの切れ目を軽く両端から押すようにして開き、そこに先のなめろうを詰める。折角のナスが破れないように注意を払う必要があるが、できるかぎりたっぷりと盛ったほうが、見た目にも、食味にも良いと思う。そして詰めたら、5分ほど魚焼きグリルで焼く。ちなみにオリジナルではオーブントースターで焼く、とあった。これでも良いと思う。なめろうの表面に焦げ目がつくかつかないか程度のところが焼き上がりのサイン。
食べてみるとふわっとしたナスの食感がまず来て、それをかみ締めるほどになめろうの風味が広がってゆく、という具合である。そしてやがてナスとなめろうは一つの味となって、食べることで完結する料理の見本のようであった。
しかし・・・・・・どうも味が薄い。基本的にナスには何ら味付けをしないので、もう少し濃い目の味付けをなめろうに施すべきであった。そうすることで最後にナスととけあったなめろうは、もっと素敵な味を口中に演出してくれたような気がする。
そういった意味では、横に添えたいわゆる「サンガ焼き」の方が味のバランス的には良かったかな(^^ゞ とはいえ、今を旬に迎えた秋茄子ということもあり、旨かったことには違いないのだが・・・。
もとは漁師料理のなめろうが、こんな素敵な形で秋茄子を演出してくれる、また秋になると食べたくなりそうな一品である。もうアジは食べ尽くしてしまったけれど・・・
 続きを読む
続きを読む
2007年09月26日
アジのなめろう
 アジと言えばタタキを思い出すが、「なめろう」も隠れた名品の趣がある、と思っている。殊に酒のアテという意味では、こちらのほうが万能選手かもしれない。
アジと言えばタタキを思い出すが、「なめろう」も隠れた名品の趣がある、と思っている。殊に酒のアテという意味では、こちらのほうが万能選手かもしれない。作り方を簡単に書いてみる。アジは3枚に卸して、皮と腹骨を漉き取る。小さなアジを使うときは、骨抜きで血合に残った小骨を抜き取る。大き目のアジ(今回は30cmクラスのアジを使ったので、こちらの方法をとった)なら、血合に沿って上下に身をサクどりし、血合骨の部分だけを薄く包丁で切り取ればよい。いずれにしても、そのまま叩いて供する料理なので、「小骨は面倒だからそのままでいいや」的な作り方は、舌触りの点からもお奨めできない。この一手間は、大きく味に影響するものと心得よう。
さて、下処理を終えたアジは、タタキにするときと同じように小さめに切っていく。そこに大葉を千切りにしたものとショウガのみじん切り、それに大さじ1程度の味噌を載せて、包丁で叩いていく。アジを切るときは柳葉包丁が良いが、叩くときは柳葉だと刃が薄く軽いので、少々時間がかかる。新鮮なアジはあまり叩き過ぎたくないので、できればなるべく肉厚の出刃包丁を使うことをお奨めする。これなら刃の重みで、かるく叩いていても十分タタキになる。時々包丁で掬い取るように全体を混ぜながら、粘りが出てくるまで叩けば、出来上がりである。
食べるときは、好みで万能ネギの小口切りなどを添えると良い。もちろんそのままでも美味しい。今回は食べる前に、あまっていたカボスをちょっぴり絞ったが、これもまた清涼感を添えてくれて良いものである。
チビチビとつまみながら、日本酒をやるもよし

豪快に口に放り込んで、冷えたビールを飲み干すもよし

・・・その他、要するに何でもよし(笑) 続きを読む
2007年09月21日
アジのムニエル・野菜ソース添え
 アジのムニエルを作ってみた。ムニエルというとバターを使う。バターの風味でそれなりに美味しくできることも確かだが、ソースまで重いとそれなりにしつこい料理という印象もある。
アジのムニエルを作ってみた。ムニエルというとバターを使う。バターの風味でそれなりに美味しくできることも確かだが、ソースまで重いとそれなりにしつこい料理という印象もある。そこで、ソースにはフレッシュな野菜を使ったレシピを参考にしてみた。
アジは、下処理したもの(ウロコ、エラ、ワタを取ったもの)に塩、コショウをして、小麦粉をまぶす。まぁムニエルやソテーの基本的な手順で良い。特筆すべきは何もないが、満遍なくかつ薄くまぶす。これが案外難しく、なかなかキレイにできない~
 できなくても、それなりには仕上がるので、とりあえずはあまり厚く粉をつけすぎないことに留意すれば、それでよいと思う。厚くつけてしまうのは、いろんな意味でいただけないので、それくらいなら多少粉のついていないところもあるかな、くらいでやめておくほうが個人的にはいいと思う。
できなくても、それなりには仕上がるので、とりあえずはあまり厚く粉をつけすぎないことに留意すれば、それでよいと思う。厚くつけてしまうのは、いろんな意味でいただけないので、それくらいなら多少粉のついていないところもあるかな、くらいでやめておくほうが個人的にはいいと思う。ソースに使う野菜は、タマネギ、ピーマン、それとトマトである。トマトは湯むきしたものを1cm角に切っておく。他の野菜もトマトの大きさに合わせて切って、スタンバイOK。
いよいよ焼きだ。まずは熱したフライパンにバターとサラダ油を同量で入れる。今回はアジ4尾を焼くので、それぞれ大さじ1強くらいずつ入れた。バターが溶けて、サラダ油となじんだらフライパン全体に広げて、アジを投入する。このとき皿に盛りつけるときに頭が左側になることを考慮して、皿の上側になる側をまずは下にして焼いていく。こちらは見える部分なので、極力おいしそうにパリッとした感じに焼き色がつくまで、そのまま焼く。時々そっと持ち上げてみて、いい感じにキツネ色の焼き色がついたら、裏返してもう片面も焼く。裏返したら、見た目よりもきちんと火が通り、かつ火を通しすぎて硬くなったり、あるいは焦げたりしないように注意する。裏返すまでは見た目重視、裏返したら火の通り加減重視だ。見た目も重要・・・と思うので

さてアジが程よく焼けたら、皿に取り、フライパンを一度キレイにする。キッチンペーパーでふき取るのが簡単でよいが、焼いたときにフライパンに付いた小麦粉のかすはそのままにしておくと苦味が出るので、きれいに拭くことが肝要!
フライパンを掃除したら、あらためて今度はバターだけを、アジを焼いたときの倍量(つまりアジを焼く際のバター+サラダ油と同量)である。今回の場合、大さじ2強ってことになる。
バターが溶けてきたら、切った野菜を一気に放り込む。よく火の通りにくいものから、と言うが別に火を極力手早く通す中華料理を作るわけではないので、気にしなくていい。全部一気に放り込むのが基本だ。それでも気になるという方は、まぁタマネギ→ピーマン→トマトって感じかな。おいらは気にしないので、よく分かりません・・・

時々フライパンをあおって、バターを全体になじませながら、野菜に火を通していく。トマトから水分が出て、タマネギが透き通ってくるとだんだんソースっぽくなってくる。フレッシュ感を残すため、トマトの形が崩れて、タマネギが透き通った感じくらいで今回はやめておいた。ここら辺の火の通し加減は、食べる方の好みでよい。あまりマニュアル主義にならずとも良い部分だと思う。
できあがったソースを皿に盛りつけたアジの上にかけたら、出来上がりである。よりさっぱり感を出したい方は、食べる前にレモンを絞ったりしても良いかもしれない。(私はやらなかったが・・・) アジだけに少々小骨が多く、若干食べにくい印象はあるが、アジとバターはなかなか好相性である。表面をパリッと焼くことができれば、香ばしい皮の部分とホクホクの身の部分のコントラストが絶妙になるはずである。ゆえにアジを焼くときは、是非とも真剣勝負のつもりで焼いてください。一見簡単な調理法だけに、そういったことで結構差ができる。まぁ今回は75点くらいかな。
でも野菜ソースのフレッシュ感も加わり、重くなりがちなムニエルも比較的あっさりと、ヘルシーな感じでいただける。女性にも受けそうな料理だと思う。 続きを読む
2007年09月14日
アジの干物
 アジといえば・・・フライと書いたが、実はこの干物ってやつも捨てがたいものである。ある程度保存性も高い、これも一つの決め手だろう。
アジといえば・・・フライと書いたが、実はこの干物ってやつも捨てがたいものである。ある程度保存性も高い、これも一つの決め手だろう。そう思い、いつまでも冷凍庫に放り込んで、スーパーで買うアジと化してしまう前に干物を作ってみようと思い立った。
まずは干すためのネット・・・。オ●ンピ●クで1,000円チョイで売ってました。一応アウトドア製品では、それなりに名の通ったメーカー品なので、安心

アジは腹から開いて、背びれぎりぎりまで包丁を入れて、開く。いろいろ流儀はあると思うが、個人的には尾側から包丁を入れて、中骨に沿って開いていき、腹骨のところは少し慎重に腹骨を一本一本切り離しながら進めると存外簡単にできた。アジの場合、腹骨も比較的やわらかいので、開き易い。
開いたアジは、あらかじめ作っておいた10%の塩水に放り込む。このとき、開いたアジ全体が浸かる程度の量の塩水を予め用意しておくことが要諦である。ちなみに海水の塩分濃度が約3~4%くらいだそうな。とするとここで浸ける塩水はかなり濃い。塩水に浸けたら、冷蔵庫に約一時間ほど入れておく。これで十分、塩分が浸みこむ。
ちなみに今回の教訓・・・塩水から取り出したアジは、干す前に表面の塩水を十分にふき取ったほうが良い。そうしないと食べるときに、かなりショッぱい~~~

干す時間は、干す場所の状況とかにもよるが数時間~一日程度。表面全体が乾いた感じになるまでは、少なくとも干しておこう。干しあがったら、すぐに食べないものはラップして、冷凍庫で保存すればよい。
干しあがったら、後は焼くだけ。魚焼きグリルで、今回の中アジサイズなら10分かからずに焼ける。このサイズのアジは、干して焼くことで頭から尻尾まで余すところなく食べられる。もちろん中骨も、何の問題もなくイケる。ほんの少し醤油をたらした大根おろしを添えたら、至福の味が楽しめること請け合いだ。だけど↑の教訓だけは、ゆめゆめお忘れなく!
あぁ、のどが渇いた~(笑) 冷えたビール、もう一杯!!
 続きを読む
続きを読む
2007年09月13日
アジの粒マスタードフライ
 アジといえば、大好物な料理がこれ、「アジフライ」です! タタキなんかもいいけれど、このアジフライという料理も、まずまず定番ながら、実に美味しいと思います。
アジといえば、大好物な料理がこれ、「アジフライ」です! タタキなんかもいいけれど、このアジフライという料理も、まずまず定番ながら、実に美味しいと思います。そのアジフライをちょっと一工夫。普通は、アジフライといえば背開きですが、この場合、3枚おろしにします。もちろん背開きでもいいですが・・・3枚おろしのほうが簡単ですからね~(笑)
3枚におろして、腹骨をすきとった身にほんの軽く塩、コショウをしておきます。この後、粒マスタードを使うので、特に塩は軽めで十分です。
身側にスプーンなどで粒マスタードを塗ります。量はお好みですが、あまりつけ過ぎずってところがいいと思われ。。。
あとは普通にフライの要領で、小麦粉→溶き卵→パン粉の順でつけて、揚げるだけです。ちょっと揚げすぎました~

実は今回、底が平らで炒めたりしたものがくっつかない加工のしてある中華鍋を購入したので、その鍋で揚げてみました・・・が、すっかりフライヤーに慣れきってしまっていたので、温度調整が難しく、少し温度が上がりすぎて、表面が黒くなってしまいました。。。 大体170~175℃を目安に揚げれば、OKでしょう。
 残った中骨と頭は、から揚げにしました(無駄なく~
残った中骨と頭は、から揚げにしました(無駄なく~塩・コショウをして、片栗粉を軽くまぶしたら、フライよりちょっと高めの温度で揚げれば出来上がりです。某和食系ファミレスで、ランチに「アジのたたき丼」をオーダーしたときに、このから揚げが付いてきて、気に入ってしまいました。中骨の骨センベイは、これまた定番ですが、頭もから揚げにして、いと旨し、です。できれば一度揚げたものを冷ましてから、二度揚げするとよりパリッとした歯ざわりが楽しめます。
今回釣った味は、いわゆる中アジサイズで、フライにも骨センベイにもジャストサイズでした♪ このフライには、タルタルソースよりもいわゆるソースのほうが合いますね、きっと

フライもから揚げも、なかなか好評です。あっという間に完食しました。そしてビールもあっという間に・・・
 続きを読む
続きを読む
2005年05月03日
アジネギ
 ウロコ(ゼイゴ)と内臓を処理したアジに軽く全体に塩をしてしばらく置きます。ごく薄く油を引いたフライパンでアジを両面焼き色がつくまで焼いていきます。アジに火が通ったところで醤油と日本酒同量合わせたものを全体にかけ回し、アジの隙間に適当な長さに切ったネギを並べていきます。ネギに火が通るまで焼いたら出来上がり。ネギの風味の付いたアジが旨いのは勿論ですが、アジと醤油の染みたネギも美味しいです。 続きを読む
ウロコ(ゼイゴ)と内臓を処理したアジに軽く全体に塩をしてしばらく置きます。ごく薄く油を引いたフライパンでアジを両面焼き色がつくまで焼いていきます。アジに火が通ったところで醤油と日本酒同量合わせたものを全体にかけ回し、アジの隙間に適当な長さに切ったネギを並べていきます。ネギに火が通るまで焼いたら出来上がり。ネギの風味の付いたアジが旨いのは勿論ですが、アジと醤油の染みたネギも美味しいです。 続きを読む