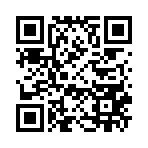2007年10月26日
茄子のなめろう焼き
 しばらく溜めていた料理ネタもこれで一段落であるが、「スローライフとしての釣り」で紹介した雑誌「サライ」に「秋茄子のなめろう焼き」というオリジナルレシピが載っていた。今回の料理は、これを真似たもので、オリジナルのほうではアジではなくマイワシを使っていた。
しばらく溜めていた料理ネタもこれで一段落であるが、「スローライフとしての釣り」で紹介した雑誌「サライ」に「秋茄子のなめろう焼き」というオリジナルレシピが載っていた。今回の料理は、これを真似たもので、オリジナルのほうではアジではなくマイワシを使っていた。オリジナルレシピでは、茗荷やら、松の実やら、果ては山椒の佃煮まで入れていたが、我が一般庶民の家庭にそれらのものが常備されているはずもなく、なめろうは普通にアジに味噌、大葉、生姜を入れて粘りが出るまで叩いたものである。ただし普通のなめろうほど細かく叩かず、少し身の粒々感が残る程度がいいみたい!
さらにオリジナルレシピによると味噌は「ハナマルキ味噌」という指定があるが、これは単にスポンサーの関係と思われる
 まぁ引用させていただいた関係で、ここでも軽く宣伝させていただくことにしよう~
まぁ引用させていただいた関係で、ここでも軽く宣伝させていただくことにしよう~
さてなめろうを作ったら、なめろうの器ともなるナスの仕込である。写真では、ナスのへたをとってしまったが、オリジナルではつけたままだった。どうやらつけたままの方が、見栄えは良いように思われる。もし作る方がおられるなら、へたはつけたままにしておこう。文字通り「へた」なことをしてしまったものである・・・・・・

ナスは洗って、水気を十分に拭いたら、縦に深く一本、包丁で切れ目を入れる。それを170℃の油で素揚げにする。揚げることでナスの色がとても良くなるので、ここでの素揚げは、火を通すことより専らナスの彩りに気を使うべきである。
さて素揚げしたナスの切れ目を軽く両端から押すようにして開き、そこに先のなめろうを詰める。折角のナスが破れないように注意を払う必要があるが、できるかぎりたっぷりと盛ったほうが、見た目にも、食味にも良いと思う。そして詰めたら、5分ほど魚焼きグリルで焼く。ちなみにオリジナルではオーブントースターで焼く、とあった。これでも良いと思う。なめろうの表面に焦げ目がつくかつかないか程度のところが焼き上がりのサイン。
食べてみるとふわっとしたナスの食感がまず来て、それをかみ締めるほどになめろうの風味が広がってゆく、という具合である。そしてやがてナスとなめろうは一つの味となって、食べることで完結する料理の見本のようであった。
しかし・・・・・・どうも味が薄い。基本的にナスには何ら味付けをしないので、もう少し濃い目の味付けをなめろうに施すべきであった。そうすることで最後にナスととけあったなめろうは、もっと素敵な味を口中に演出してくれたような気がする。
そういった意味では、横に添えたいわゆる「サンガ焼き」の方が味のバランス的には良かったかな(^^ゞ とはいえ、今を旬に迎えた秋茄子ということもあり、旨かったことには違いないのだが・・・。
もとは漁師料理のなめろうが、こんな素敵な形で秋茄子を演出してくれる、また秋になると食べたくなりそうな一品である。もうアジは食べ尽くしてしまったけれど・・・
 続きを読む
続きを読む
2007年10月25日
メバルの昆布締め(自己満足編)
 相も変わらず、メバルといえば「昆布締め」であります
相も変わらず、メバルといえば「昆布締め」であります
しか~し、わざわざしつこく投稿したのは、この記事で書いた「淡島マリンパーク」内の工房で作った手びねりの自作皿を自慢 σ(`・・´ ) したかった(するほどのものではないが・・・・・・)からです。まぁ素人丸出しではありますが、旅行のたびに何度か陶芸工房に行った成果(というほどのものではないが・・・・・・)か、今までよりは少しまともな出来だったので、とりあえずお披露目してみようかなと思い立ちました。補足すると、この前の記事に書いた「アナゴの山椒揚げ」の皿は、相方作であります♪
といっても、自分たちでやるのは粘土をこねて、成形するところまで。色付けなんかは、工房のプロ(?)のお姉さんがやってくれて、後日(一ヶ月くらい)送ってくれます。作るときも、お姉さんが指導してくれるので、まぁ何とかできました(笑)
で、タイミングよく送られてきたので、折角だから昆布締めでも並べてみるかという訳です

肝心の昆布締めは、いつも通り昆布を日本酒に漬けて戻したわけですが、どうもほかの事と並行で昆布を戻したら、戻しすぎて肝心の昆布のエキスがかなり日本酒に流出してしまったようで、半日以上締めた割には、今ひとつ昆布の風味が物足りない昆布締めとなりました。まぁ素人の手作りの皿には、この程度の出来の料理が却って似合うのかもしれませんね~(笑)
という訳で、昆布締め自体は、ちょっとイマイチなものになってしまいました。後に残ったのは・・・自己満足だけかな~
 続きを読む
続きを読む
2007年10月23日
アナゴの山椒風味揚げ
 オリジナルレシピの正式な料理名を忘れたので、雰囲気で勝手に名づけてしまいました。アナゴで揚げ物というと、一般に天ぷらのイメージがあると思いますが、ちょっと目先を変えたこんな揚げ物はいかがでしょう。
オリジナルレシピの正式な料理名を忘れたので、雰囲気で勝手に名づけてしまいました。アナゴで揚げ物というと、一般に天ぷらのイメージがあると思いますが、ちょっと目先を変えたこんな揚げ物はいかがでしょう。簡単かつ美味しいですよ♪
開いたアナゴは、ボウルに醤油大さじ1+山椒小さじ1/2の割合で混ぜたものに10分ほど付けておきます。漬けるタレの量は、前記の割合でアナゴに合わせて加減してください。10分漬けると白かったアナゴの身がほんのり醤油色になって、山椒のいい香りが・・・・・・この段階で(お腹が空いていたので
 )食欲中枢はレッドゾーンに突入!
)食欲中枢はレッドゾーンに突入!それを堪えつつ、後工程へ。漬け終えたアナゴは一口大に切って(オリジナルでは上げた後に一口大に切っていました。逆に漬ける前に切っても良いと思います)、片栗粉を満遍なくまぶします。これで下ごしらえは完了です~

さて揚げに入ります。といっても、揚げるのはフライパン。そこに少し多目のごま油を入れて、熱します。アナゴは裏返しながら揚げればよいので、全体が浸かるほど入れなくても大丈夫です。要するに揚げ焼きといった感じですね
 裏返して両面キツネ色になるまで揚げればOKです。とはいえ、通常よりも、結構ごま油を使うので「勿体ない」という方は普通のサラダ油でもいいかもしれません。ただカラッ、サクッとした食感といい香りを添えるという意味では、ごま油はお奨めです。安いので十分だと思いますので、できれば最初はオリジナルレシピ通り、ごま油でやってみてください。
裏返して両面キツネ色になるまで揚げればOKです。とはいえ、通常よりも、結構ごま油を使うので「勿体ない」という方は普通のサラダ油でもいいかもしれません。ただカラッ、サクッとした食感といい香りを添えるという意味では、ごま油はお奨めです。安いので十分だと思いますので、できれば最初はオリジナルレシピ通り、ごま油でやってみてください。冷えたビールを準備したら、いよいよ食べます
 まずさくっとした食感、そうしてかみ締めるとふんわり香る山椒、さらに衣に包まれてふわりと仕上がったアナゴにしみこんだ醤油の旨みが広がります。
まずさくっとした食感、そうしてかみ締めるとふんわり香る山椒、さらに衣に包まれてふわりと仕上がったアナゴにしみこんだ醤油の旨みが広がります。サクサクとした食感のせいか、いくらでも食べられそう。今回は押し寿司に使った一番大きいアナゴ以外の三本をこの料理に使いましたが、あっという間に完食と相成りました。やっぱりアナゴと山椒は、好相性ですね。そして白焼きや蒲焼きとも違うサクッ、ふわっの食感、またお気に入りが一つ増えました! 続きを読む
2007年10月22日
アナゴの押し寿司
 アナゴはぬめりを良く取ってから、普通に背開きにします。そして残った頭(内臓は除く)と中骨も使います。
アナゴはぬめりを良く取ってから、普通に背開きにします。そして残った頭(内臓は除く)と中骨も使います。まずは寿司に塗るツメの準備です。頭と中骨は、魚グリルでさっと焼きます。このとき中骨に残った血合いなどはきれいに洗っておきましょう。
次に鍋に酒とみりんを1:3の割合で入れて、一度沸騰させて煮切ります。そこにアナゴの中骨・頭を入れたら、やや多めに砂糖を入れます。砂糖はツメの甘味ととろみを補ってくれる重要なポイントなので、味を見つつ入れてください。結構入れちゃっても大丈夫です。砂糖が溶けたら、みりんよりやや多目の醤油を入れます。ここでもう一度沸騰させて、沸騰したら弱火で約30分煮詰めます。これでとろーりとした、ちょっと甘辛いいい感じのツメができました。
アナゴは開いたものを魚焼きグリルで焼くだけです。ただ普通に焼くと、皮目が丸まってしまい、押し寿司の見栄えが悪くなりそうだったので、金串を打って焼きました。金串は一本●十円程度で打ってますので、数本買っておくといざというときに重宝しますヨ!(ただし決して出番の多いものではありませんが・・・・・・)
さてアナゴは、大きさにもよりますが、10分程度焼けばOKだと思います。あまり焦がさない程度で、硬くなりすぎないようにふっくらと焼き上げることを意識しつつ見ていれば、いい感じに焼けると思います。
あとは作っておいた酢飯(相方任せですが、寿司酢は酢に砂糖と塩少々。それに今回は大葉のみじん切りを混ぜ込んでみました)を市販の押し寿司器に詰めて、その上に焼いたアナゴを載せます。そうしてギュッと上から押して、さらに適当な重石をしたまま10分ほどなじませます。このなじませるという工程を省くと、切るときにバラバラになるので、是非やってください。
あとは切り分けた押し寿司のアナゴの上に作ったツメを塗って完成です。
アナゴもいい感じにふっくらで、ツメのとろとろ加減もばっちりでした。頭や骨から出たゼラチンがいい感じにとろみを出してくれましたね。さらに酢飯に混ぜた大葉も、口に含むといい香りを演出してくれて、即興の工夫にしてはなかなかよかったと思われ。。。
久しぶりのアナゴが堪能できた一品でした。 続きを読む